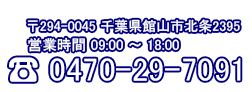釜戸と囲炉裏があるワンルーム平屋で、家族4人暮らし

【田村佳子さん】
<ご紹介するのはこんな方>
田村佳子さん(45歳)
南房総市在住
家族構成 4人(パートナーと9歳の長男、1歳の長女)
以前の居住地 東京都杉並区から館山市へ移住
移住スタイル 定住
都内から南房総に移住した田村さんは、館山市船形の借家でパートナーと暮らし始めました。その後、南房総市三芳地区の環境が気に入って賃貸物件を探しましたが、見つからず。221平方メートル(約70坪)の土地だけが手に入ったため、そこに家を建てることに。どんな条件で家造りを始め、どんな家ができ上がったのでしょうか。マイホームでの暮らしや、住み心地について話をうかがいました。
こだわりの平屋を自然素材で

【玄関へ続くアプローチ】
田村さん宅に足を踏み入れると、まずは香り豊かなハーブが植わるアプローチ。玄関を開けると、お宿のような雰囲気に包まれた、艶やかで広々とした土間の空間が現れました。土間には薪ストーブが据えられ、小上がりから板の間、囲炉裏部屋から奥の寝室までつながっています。天井には立派な丸太が使われ、台所と寝室の間にも壁がなく、仕切りのない広々としたワンルームのつくりです。

【囲炉裏がある部屋は畳、その向こうは板の間】
木、石、土などの自然素材を、可能な限り近隣から集めて建てる平屋の家。それが、家づくりでのこだわりでした。住んでいた船形の家は2階建てで、全部で6部屋ありました。けれど、実際に使っていたのは2部屋だけ。使い勝手が悪かったので、部屋数が少ない平屋であることは、田村さんにとって外せない条件でした。
陰陽道の考え方を参考にして、朝日から正午までの時間は太陽の光がたっぷり入るように玄関や台所は東側に。逆に午後からの西日は入らないように、西側には木の扉が付いた小窓のみを設置しました。台所には釜戸があり、薪ストーブと囲炉裏、薪風呂と、薪火を使う暮らしをしています。

【釜戸の横にあるタイル張りの流し台】
「火を使って料理をすると、魚は臭みがとれるし、野菜は出汁が出てなんでも美味しくなります。薪で炊いたお風呂は水がまろやかに。そして何より、炎の揺らぎを見ているとそれだけで、仕事の疲れが取れます」と、炎とともにある暮らしがとても気に入っている様子です。田村さんの周りには同じように薪火の暮らしをしている友だちが多く、彼らに勧められて取り入れたそうです。
田村さんは東京で派遣看護師として働いていたことがあり、さまざまな介護施設やデイサービスに出入りしていました。「だいたいの施設は落ち着かなく過ごされる利用者さんや、時間や業務に追われたスタッフの方でピリピリとした雰囲気の所が多かったですが、1カ所だけ、ゆったりとした空気が流れている施設がありました。ほかと何が違うのだろうと観察したときに、触れた壁が土壁なことに気付いて『これだ!』と確信しました」。そう話す田村さんに、この家の一番のお気に入りを聞くと、「土壁」と即答。
「お年寄りも赤ちゃんも、心穏やかになれる空間。人が人らしく生きるために、こういう場所が必要だと気付きました」と、当時を振り返りました。
手づくりの庭から
朝起きたら、神棚の水を換えて家族揃って参拝し、手づくりした梅肉エキスを自家製の薬草茶に入れて飲み、一日がスタートします。

【小さな田んぼの向こうにある自宅】
今春、家の隣の敷地に小さな手作りの田んぼを3枚作りました。1枚は田村さん、隣は9歳の長男の田んぼで、その隣に1本だけ植わっているのは、1歳の長女の田んぼです。「田んぼを通じて、近所の人との交流が増えました」と田村さんは言います。日照りが続く今夏は、お風呂の残り湯を田んぼに撒くのが日課なのだとか。

【田んぼの横にある畑からハーブを収穫】
2019年12月に自宅が完成したときから、こつこつと庭づくりにも精を出しました。当時植えた小さな苗木のティーツリーは今、大きな木へと成長し、その木陰でBBQを楽しめるようになりました。「全てのシーズンに1つは花があるように」と、クロモジや月桃、バナナ、たくさんのハーブが植えられていて、それらを使ってお茶やチンキを作ったり、料理に使ったりして楽しんでいます。
呼吸する家に住んで分かったこと
自然素材で造られた家で毎日を過ごしていると、それが当たり前になって特別に感じていませんでしたが、旅先でシティホテルに泊まって気づいたことがあるそうです。
シティホテルは、セントラルヒーティングで空調が管理されていて、窓を開けることができませんでした。温度は快適に設定されていましたが、眠りについたとき「自分が真空パックの中に閉じ込められているような気持ちになった」と言います。眠れない夜を過ごし、自然素材で呼吸している自宅の良さを、再認識しました。
都会から友だちが遊びに来ると、ほぼ全員がその場に寝転び、しばらく動けなくなってしまうほどリラックスするそうです。普段意識していなくても、自然素材で呼吸をしている空間に身を置いてみると、身体は自然に反応するのかもしれません。
解決策を出すのが楽しい
長男が4歳のときに完成した家の土間は、広いスペースを利用してランニングバイクの「ストライダー」で走ったり、縄跳びの練習をしたりする場所でした。その後長女に恵まれ、家が少し手狭に感じられるようになります。
9歳になった長男は、「自分のスペースが欲しい」と言いだし、家の設計をしてくれた設計士に相談し、長男用にロフトを作る案が浮上。土地があればティピ―(アメリカンインディアンが利用する移動式住居)を建てたいという案もあるそうです。
最初の土間は、土埃が舞って掃除が大変でしたが、試行錯誤を重ねて上から漆喰を塗ることで、掃除しやすい艶やかな土間になりました。もともと収納や下駄箱がないため、手に入った桐タンスを棚に活用し、「問題が出るたびに解決策を出すのが楽しい」と、田村さんは言います。

【タンスを置いて収納スペースを増やした土間】
田村さんはもともと東京での生活が大好きで、オーガニックフードに興味はなく、一生都会に住むつもりだったそうです。当時の彼女を知る友だちがここを訪れ、釜戸で玄米を炊き、囲炉裏で自家製塩を作る姿を見ると、その変貌ぶりに驚くそうです。移住前はバックパッカーとして50カ国を旅してきたこともあり、「順応性があると思う」と笑う田村さん。
その都度解決策を考え、柔軟に順応してきたからこそ、今の暮らしに辿り着いたのでしょう。
移住を考えている人へのアドバイス
「ピンときた家は、絶対に見に行った方がいい。思っていたのと違うって思っても、何かが引っかかったら見に行ってみるべき。きっとそれが、自分に合っているものだと思うので。
最初から『こうしよう』って決めて、『こうじゃないといけない』っていうよりも、意外といろんなことが起こるから、何か問題が起きたら『こうしたらいいんじゃないか』って解決しながら進んでいくと、長い目で見れば、楽しく暮らしていけると思います」
(※本記事は、2025年8月に取材・撮影を行った際の情報をもとにしています)